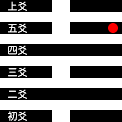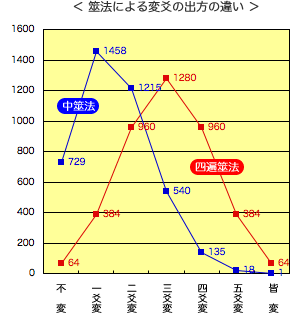では、思いっきり maniac に。
易占で広く行われている中筮法は初爻から上爻まで6回 筮竹を割って卦を出し、【坤】¦¦¦の老陰・【乾】|||の老陽(= 変爻)があればそれを裏返して之卦を求める。
孔子が編したということになっている十翼の一「繫辭上伝」の記述を根拠として、南宋の大儒である朱 熹[朱 子]が「周易本義」の「筮 儀」のように復元した所謂 本筮法であれば、その竹割りは18回に及ぶ。かつ操作が入り組む。
中筮法は出典は何なのか、ともかく、変爻の確率に関する限りは本筮法と同じ。
時代が下って操作が大きく簡略化されて、中国伝来とも江戸中期の“卜者”平澤 随貞によって考案されたとも言われる三変による略筮法は内卦・外卦を直接 出した後に一つ爻位を求めて之卦をつくる。
これらの筮法に対して、四遍筮(四‘変'筮法ではない)は之卦を元卦(本卦とは言わない)の爻変によってではなく、独立した操作によって出すという異色の筮法で、元卦の内卦・外卦、之卦の内卦・外卦と計4回 筮竹を割る。
関西で長年 実占研究に取り組まれた故・紀藤 元之介 氏が考案したもので、正しくは「元之筮法」という。もっとも、之卦を独立した操作によって出すやり方は江戸中期の新井 白蛾より古い易者である吉川 祐三の文献にも見られる。
この四遍筮について、はたして日常 我々が関わる占事で使用して卦を得るものか、以前から疑問があった。やはり之卦の求め方が引っ掛かる。一つの卦の四象・八卦の老の極まりに陰陽の転換を見るのが之卦でしょう、と思うから、四遍筮では従来のような元・之の連関のない二つの卦を出している気がしてならない。これなら元卦にどれ程の意味があるのか、之卦だけ求めればいいのではないか、と考えたりもする。
大きく言えば、筮法の機能が占事の背景となる現実に合っている限り、一連の操作が一つの筮として執り行われる限り、認められるものだとは思うのだが・・・。
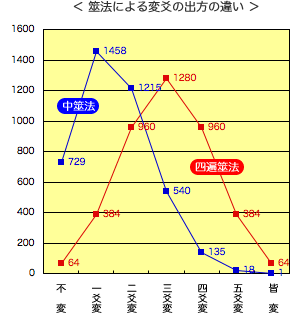 |
| |
四遍筮は値を64倍して分母を中筮法と同じ 4,096 に揃えた。中筮法と比べると高低差は約1/73だから実際のグラフの勾配はこれより極めてなだらか。
未確認だが、本筮法も中筮法と同じ線を描くのか? 実際の老陽・老陰の出方は3/8に近いが・・・。
また、爻変が常に一つの三変略筮法をグラフに表すと、一爻変のところに垂直に直線が立つ。 |
| |
四遍筮の爻変を確率の点から見る。
例えば、中筮法では変爻の数は一つか二つとなる場合がほとんどで、これに次に出やすい不変(=【乾】・【坤】の爻を得ないこと)を加えると変全体の約83%を占める。之卦に出る卦の種類は一爻変の場合6、二爻変の場合15、不変ではそのまま1、で計22卦。さらに三爻変・四爻変は出る確率が大きく下がり、五爻変以上となると実際にはほとんど出くわすことがない。こちらは中筮法を使うことは少ないが、かつて変四つがあっただけだ。
中筮法では最も出易い一爻変と最も出難い皆変の出方の差は実に 1,458 倍にもなる。
これが四遍筮になると実は三爻変が最も多く出る。次に、少し確率が下がって二爻変と四爻変が同率で、~不変と皆変(= 六つの爻 全てが変じること)が最も出る確率が低い。二・三・四爻変で変全体の約78%に。之卦に出る卦の種類は三爻変が最高で20になり、二・三・四爻変だけで全64卦中、50もの卦が出てしまう。
それで、之卦へのパターンが最も多い三爻変と1パターンしかない不変・皆変の出方の差は20倍に留まるので、中筮法だけをやっていたら確率1/4,096 で一生に一度も経験しないかも知れない 11【地天泰】¦¦¦|||→ 12【天地否】|||¦¦¦(← 左を上に。以下 同じ)なんて驚くべき皆変も1/64の確率で生起するのだ。不変も同率。
四遍筮では之卦を元卦とは別に求めるから、当然 全ての卦が1/64の同率で出る。つまり、之卦は元卦の陰陽配列に近い卦ほど出やすい、という卦の重点分布がない。これは際だった特徴だし、卦同士の関係のあり方の点でも問題を含んでいる。
以上から、四遍筮は元卦と之卦の間の卦同士のパースペクティヴや関係性が従来のそれとは全く異なるので、この筮法を用法や読卦の点など本筮法・中筮法と同じ様に扱ってよいわけではないらしいことが判る。もっとも、問いに対して排他的に卦・爻を得て占筮なのだから、こうした筮法の構造が頭に入っておらずに筮を執り行うこと自体おかしいが。
尚、以上の確率はあくまで確率で、実際にはこちらの三変筮法と中筮法の記録で本卦を例にしてみると、サンプル数の点は微妙だが、不思議にも、最もよく出る上爻と最も出ることの少ない四爻で出方に約3倍の差がある。
易という機構の上で筮法を創作するからには、当然のこととして、之卦の出方が占事とする分野の現実に合理的に合致している必要がある。例えば、「進むべき道はAか、Bもあるが」という占題を扱うのに、答えが三つも四つも示されがちというのでは筮法として組み立てが怪しまれる、ということ。だから、こんな筮法をわざわざ創ったというのにはそれなりの理由がある筈だ。

山雷頥 |
|

地天泰 |
|

山地剥 |
| |

五爻変 |

四爻変 |

四爻変 |
|

火澤睽 |

五爻変 |

澤山咸 |

四爻変 |

雷澤歸妹 |
| |
五爻変
 | 五爻変

|
四爻変
 | |

地澤臨 |
|

風澤中孚 |
|

山風蠱 |
|
|
| |
恋愛の卦【澤山咸】を例に。
実は四爻変・五爻変は興味深い。中筮法でこれらの変化がほとんど見られないことが不思議だ。 |
| |
しかし、その意味で明確な理由が判らない。
四遍筮というとまず変爻の数の多さが特徴になるが、これが本筮法・中筮法だと、確率的に5・6回に1回は不変になってしまって之卦がないので、判断がしにくい難点がある。「状況に変化の兆しが見えず」などの結論になってしまうから、それで将来についての問いに応じたことになるのか? と疑問が湧きもする。そこで、六爻を天・人・地の三才に配当したものなどを持ち出すわけだが。
四遍筮なら不変卦はわずか64回に1回で、変化のバリエーションも極めてばらけ傾向。だから、以上を考えると、四遍筮は事態内部の何かしら複雑な変化を読むケースには合理性が増すかも知れない。状況の変化の機微を見るケースならば二つ~四つの変化が常態と言えるような占事・・・ちょっと具体的には思いつかないが、その点が一つ挙げられる。
ただ、三・四爻変は当たり前なんてことだと卦読みにあたって爻辭は使いにくくなる。少なくても従来の占法り限りでは。
この筮法に限らず、爻辭を使うならば、二爻変以上の場合は、歴史的に異論の多い朱 熹[朱 子]の七考占(=「左 伝」・「国 語」の占例から帰納させた爻変と占断についての七つの原則)はやはりおかしくて、本卦の彖辞および彖傳・象傳に依るべきだろうと個人的には思う(一・二爻変の場合については猶 留保)。占法家の加藤 大岳 氏は中筮法で爻辭を採るならば常に本卦のそれのみとして、之卦のは参考程度に用いるとしている。
また、四遍筮では中筮法などの場合のように之卦に出る卦の重点分布がなくてどの卦も同率で出るから、従来のような本卦と之卦の意味的な連関が大きくポイントとなる占事には不向きなのではないか。否応なく象読み重視になりそうだ(とはいえ、四爻変・五爻変で出る卦は実はなかなか興味深いのだが)。これだったら将来の状況を問いたい場合は之卦だけを求めればいいのではないか、との疑問も湧く。
四遍筮は断易[五行易]で重宝されるが、周易[易]での用途については識者のお智慧を拝聴したい。
ちなみに、紀藤氏のよく知られている射覆(セキフ = 幕などで覆い隠した物を筮をもって当てる)での占断で、17【澤雷隨】|¦|¦¦|→ 63【水火旣濟】|¦¦|¦|を得て、内卦・外卦が東西南北の方位を順番のままに表しているから覆われた物を地図と当てた例があるが、これは二爻変であり、四遍筮だからこの卦を得やすかった、というものではないだろう。
少し検証。四遍筮の場合、各変爻の出る確率の全体に占める割合が之卦に出る卦の数の全体に占める割合と一致している。つまり、皆変では之卦となる卦は当然 一つだが、確率的にその20倍 出る三爻変であれば之卦となる卦もまた20に増える。三爻変の頻度を山頂とするだけで民主的な筮法だ。
|
爻 変
|
不 変
|
一爻変
|
二爻変
|
三爻変
|
四爻変
|
五爻変
|
皆 変
|
|
変爻の出る確率
|
64
|
384
|
960
|
1,280
|
960
|
384
|
64
|
|
之卦に出る卦の数
|
1
|
6
|
15
|
20
|
15
|
6
|
1
|
|
%(計100%)
|
1.56
|
9.38
|
23.44
|
31.35
|
23.44
|
9.38
|
1.56
|
そういうことで筮法を考えると・・・本卦[元卦]に対してどの爻変も同率で出る筮式、というものを創りたくなるだろう。
すると、今度は之卦に出る卦に偏りはあるが、一爻変も不変も皆変も同じ頻度で出て、三爻変が目立つなんて特殊な状況がない。この筮式には何処に、あるいは、幾つ変化の兆しが認められるか、爻変してそこにどんな展開が現れるか、という本卦 → 之卦の意味的な連関がバイアスなく探れるだろうメリットがある。
つまりこの仕組みは、之卦となる卦の出数が、本筮法・中筮法は爻変自体の頻度に依っているのに対して、爻変内の卦の数に依っているというもの。おそらく、之卦に出る卦の偏りは最大最小差20倍で、三爻変に来る20の卦が最も登場する確率が低く、不変・皆変に来る一つの卦が最も出る頻度が高い、となるだろう。不変・皆変の出る確率は7回に1回だから中筮法の場合よりは若干 低い。
これを一番 上のグラフに表すと、4,096÷7で、縦軸の約 585 のところに水平に直線が伸びる。
非常に興味深い筮式だと思うが、数学の職人でないとちょっと作るのが難しいか。 |




















 6天水訟
6天水訟