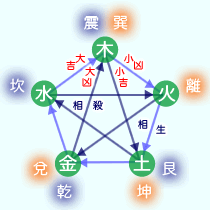|
|
| 熊崎 健翁 氏 | |
熊崎 氏は文明開化・科学礼賛にかぶれて、各地での講演では易を迷信と嘲っていたが、聴衆から「自分でやりもしないで分かるのか」と言われ、自分でやってみて、2年ほどでミイラになった。
易学徒ならご承知のように、易の64卦の並び順が現在の形に落ち着いたのは支那の後漢の頃。誰かが今ある形に決めた。
現在の最古のテキストは 1993 年 湖北省の東周時代の郭店楚墓から発見された竹簡と翌年 香港の古物市場に出回った竹簡を合わせた「楚竹書周易」で、秦の前の戦国時代の紀元前 300 年頃のもの。これには34の卦が記載され、卦序は、1【山水蒙】、2【水天需】、3【天水訟】、4【水地比】、5【地水師】~33【水火旣濟】、34【火水未濟】。現行の1【乾爲天】・2【坤爲地】がなく、【地水師】と【水地比】が逆、全34卦で終わっている。
ところが、これ以前の時代を背景とした占例が収められている「春秋左氏伝」には1【乾爲天】・2【坤爲地】もその他の卦も書かれている。
1972 年に発見された「帛書周易」は前漢の紀元前 196 年・180 年に書かれており、現在の卦名・卦序・爻辭が異なるものの、64卦が見られる。
で、姓名判断、こういう歴史の上に、いつからなのか、五つの運格(天格・人格・地格・外格・総格)とそれぞれ数の吉凶判断とか、何を根拠にそうするのか説明もない、ご商売のためのような雰囲気占いが世間に散らかっている。
| 卦序と画数による姓名判断は信じ得るか(8/11) |
|
||||||
苦労が絶えない卦だから、64卦を使ったこれを更にゴチャゴチャと弄っても機能しそうにない。
この卦はまた【艮】の門の外には【坤】の何もない画で、その真ん中を得ているので、 人々のマトモな信用を得ていない。
人は「運が悪くなる」なんて言われると、そこは避けようとする。「戒名がないと靈があの世で迷う」のご商売のデマが生きているのと同じ。姓名判断もそこに大いに乗っかっていないか…。
簡単だけれど、そんなところかな。
私見を言うと、「数」というのは宇宙共通語がまさにこれであり、卜占では易を司る神妙な摂理とこれをやり取りするが、熊崎式姓名判断というのは、卦序の根拠と、文字の画数の数え方に大いに不安を感じる。
以前「AIは卜筮に代わる機能をやがて手にするか」と質して、この卦・爻を得た。望み薄。